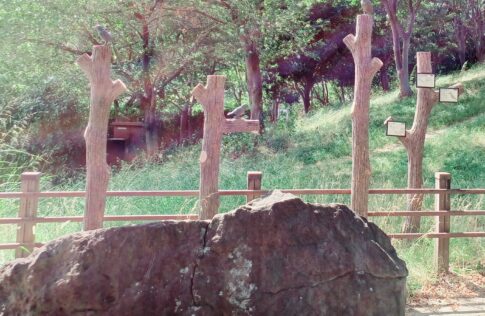親所有の土地や借地権に、子が建物を建てて診療所経営を行うことはよくあります。
法人を設立して不動産を購入し、個人や医療法人が診療を行うことも珍しくありません。
借地権ほど複雑な論点は無いと思うので、将来的な相続等を考えて、最低限押さえるべき事項や税務署へ行うべき届出を簡単にまとめました。
Contents
「土地所有者=親、建物所有者=法人」(土地の無償返還に関する届出書)
建物の名義が法人であれば、「土地の無償返還に関する届出」書を提出すれば、借地権の認定課税を避けることができます。
さらに適正地代を支払えば、小規模宅地等の特例適用が可能となり、親に相続が発生した際に相続税対策となるので、確認するようにしましょう。
地代が適正か、年によって支払い忘れが無いかなど適宜チェックする必要があります。
土地の無償返還の届出は下記のようなケースが多いので、不透明な場合は確認を行うことが肝要となります。(特に顧問税理士変更時)
・提出そのものを忘れている
・過去に提出したか否か不明
・提出した控えがあるが、記載内容が現状に即していない
参考HP:C1-63 土地の無償返還に関する届出|国税庁 (nta.go.jp)
「土地所有者=親、建物所有者=子」
この場合、個人間かつ親子間の貸借となります。
土地の無償返還の届出はそもそも法人税法上の規定であり、個人間にその制度は存在しません。
使用貸借であれば権利金の授受が回避できるため、個人で親子間貸借となる場合は、通常は使用貸借とするケースがほとんどです。
仮に一度、子から親へ相当の地代の支払を行ってしまうと、子に借地権が発生することになり、権利金部分が贈与税の対象となります。
さらに地代支払を行っていたにもかかわらず、その先で地代支払をやめると、借地権の放棄となり、子から親へ贈与があったものとされる可能性があります。
ゆえにこのようなケースで、安易に地代支払を行ってしまうと課税関係が複雑となるので注意が必要です。
同一法人で土地と建物を取得する場合
法人(特にMS法人)で建物のほか、土地まで取得するケースがあると思います。
将来的な相続発生の際に、推定相続人は相続財産を土地でなく株式で取得することになるので、株価が低い段階で自社株を贈与すれば、状況によっては相続対策となり得ます。
実質的に相続税負担を1度回避するような形となります。
(私の個人的意見ですが、将来的な推定相続人の立場を考えると、法人の土地所有は勧めません。特に医療法人の場合は、社員地位の特性を考えれば、医療法人の土地所有は避けるべきと思います。)
「借地権所有者及び建物所有者=親 → 借地権所有者=親、建物所有者=子」(借地権の使用貸借に関する確認書)
親が借地権と建物を所有していた場合、その後に下記のようなケースが想定されます。
・親名義の建物を取り壊し、子名義で建物を建てるケース
・親名義の建物を子に贈与するケース
借地権は親名義、建物は子名義となるので、通常は使用貸借となります。
ただ、客観的には借地権者が親から子に入れ替わっていて、使用貸借なのか、もしくは借地権贈与があったのかが分かりません。
個人間かつ親子間の使用貸借のため、借地権の価額は通常は0となりますが、それを敢えて把握できるようにするために、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署へ提出する必要があります。
無用なトラブルを避けるためにも、提出を失念しないことが大切です。
当然ですが、子が底地所有者に地代の支払を行うようなことがあれば、借地権の使用貸借とならず、親から子への借地権の贈与とみなされ、贈与税課税対象となります。
参考HP:No.4555 親の借地に子供が家を建てたとき|国税庁 (nta.go.jp)
「底地所有者=第三者、借地権及び建物所有者=子 → 底地所有者=親、借地権及び建物所有者=子」(借地権者の地位に変更がない旨の申出書)
子が底地所有者へ地代を支払っていたが、底地をその子の親が購入し、その後は使用貸借となることを想定します。
通常であれば、土地の賃貸借がなくなり使用貸借となるので、借地権者(子)から底地権者(親)へ借地権の贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されます。
これを回避するためには、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出する必要があります。
借地権者は元々の所有者である子のままである旨の意思表示を行うことにより、上記のみなし贈与は無かったものとして扱われます。
提出を失念すると多額の贈与税課税となるので、注意が必要です。
参考HP:B1-4 借地権者の地位に変更がない旨の申出手続(借地権者の地位に変更がない旨の申出書)|国税庁
まとめ
診療所経営を行う方は、親族間やMS法人を交えて不動産貸借を行うことが多いです。
地代算定は正しいか、契約書は完備しているか、税務署への届出は正しく行っているか等、様々な角度から確認することが必要です。